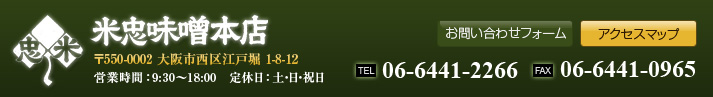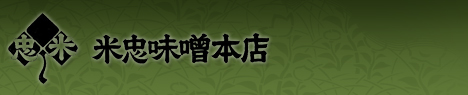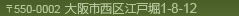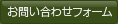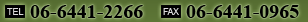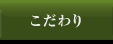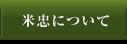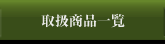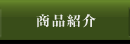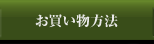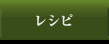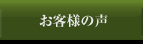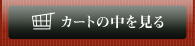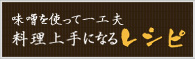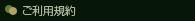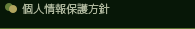̣������⤷����ī��Ⱦ���Ф����ܤˤ⤿�餵�줿�Ȥ����Ƥ��ޤ���
�������ξߤ��Ȥ������ܤǹ��פ�Ťͤ��Ԥ߽Ф����ȼ�����ˡ�ˤ�äƤĤ�����褦�ˤʤꡢ������̣�����������ޤ���������ϡ�̣����ͳ��ɤäƤ��ä����ͻ���γؼԤ����ü��ȯ���Ƥ��ޤ���
�����Ρ־ߡס���̾�ǤϡȤҤ����ɤ��ɤߤޤ������־ߡפȤ���ʸ�������θ���ʸ��Ρּ���ʤ���餤�ˡפʤɤˤ��Ǥ˸����뤳�Ȥ��顢�Ȥ��줾��̣���θ����ɤ�é���夤���ΤǤ��礦��
�������ξߤ��Ȥ������ܤǹ��פ�Ťͤ��Ԥ߽Ф����ȼ�����ˡ�ˤ�äƤĤ�����褦�ˤʤꡢ������̣�����������ޤ���������ϡ�̣����ͳ��ɤäƤ��ä����ͻ���γؼԤ����ü��ȯ���Ƥ��ޤ���
�����Ρ־ߡס���̾�ǤϡȤҤ����ɤ��ɤߤޤ������־ߡפȤ���ʸ�������θ���ʸ��Ρּ���ʤ���餤�ˡפʤɤˤ��Ǥ˸����뤳�Ȥ��顢�Ȥ��줾��̣���θ����ɤ�é���夤���ΤǤ��礦��

̣�������ߤ�̣�����Τ褦�ʷ��ˤʤäơ���̱�ο������Ȥ߹��ޤ��褦�ˤʤä��Τϼ�Į����ˤʤäƤ���Ǥ���
����ޤǤϡ�γ����Ĥ����ޤޤǡ�Ĵ̣����Ѥ�����븻����Ʀ�٤�Τ���̣�����פǤ��������ߤ�̣���ˤ��뤳�Ȥ˵��Ť����Τϳ��һ��塣���������ܤ�ƬǾŪ�����ܤ�̤����μ��θ��Ǥ⤢�ä������Ǥ�����γ�Τ���̣�������뤳�Ȥ�Ĵ̣���Ȥ��Ƥ����Ӥ������ꡢ�����餯�������������ϸ�Ω�����䤷�����ȤǤ��礦��
�����ơ�̣��������ȯŸ���פ��Ǥ����Τ���Į���塣̣���������Ǥʤ������������̣�������ΤۤȤ�ɤ������κ�����Ĥ�����褦�ˤʤäƤ��ޤ���
���λ���̣�����礭��������뤲���Ȥ�����Ǥ��礦��
����ޤǤϡ�γ����Ĥ����ޤޤǡ�Ĵ̣����Ѥ�����븻����Ʀ�٤�Τ���̣�����פǤ��������ߤ�̣���ˤ��뤳�Ȥ˵��Ť����Τϳ��һ��塣���������ܤ�ƬǾŪ�����ܤ�̤����μ��θ��Ǥ⤢�ä������Ǥ�����γ�Τ���̣�������뤳�Ȥ�Ĵ̣���Ȥ��Ƥ����Ӥ������ꡢ�����餯�������������ϸ�Ω�����䤷�����ȤǤ��礦��
�����ơ�̣��������ȯŸ���פ��Ǥ����Τ���Į���塣̣���������Ǥʤ������������̣�������ΤۤȤ�ɤ������κ�����Ĥ�����褦�ˤʤäƤ��ޤ���
���λ���̣�����礭��������뤲���Ȥ�����Ǥ��礦��

������Το����ϰ����ڡ����ܤ�٤����Х�����ƥ���1��5��θ��Ƥ��Ӥˡ�̣�����ȵ��δ�ʪ�Ȥ�����Ω�ˤ���Τ��Ȥ����Ƥ��ޤ����츫�ƿ��ˤߤ��ޤ��������Ƥǥ������ʪ�ǥ��륷����Ȥ���Ѥ����줾���ꡢ̣���DZ��ܤ���뤹��Ȥ��������������ˤ��ʤä�����ˡ�Ȥ�����Ǥ��礦�����줬�ʸ�����ܿͤˤ����뿩�δ��ܤˤʤꡢ��������������˻��ޤ�Ĺ�������Ѥ���Ƥ��ޤ�����

�Ťߤζ�����̣���ϵ��Ԥθ��ȼҲ�ǽ������줿�Τ��Ф�����̣������Τ���¸���Ȥ���ȯŸ�����褦�Ǥ���̣���ϡ����ʼ��ο�ʪ������Ǥ��ꡢ���ܲ����⤤�����Ǥʤ�����¸���䥤��������ˤ�ͥ�졢����ˤȤä��Բķ�ʿ���Ȥ�������ǤĤ�����褦�ˤʤ�ޤ����������ϡ�̣���Ť���ˤ��Ϥ������Ǥ����ΤǤ���
| �� | ����ȹ� | �������� | ���Ŀ��� | ������� | ��ã���� | �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | Ȭ��̣�� | �ò�̣�� | ����̣�� | �۸�̣�� | ����̣�� | ����̣�� |

�����鿩��Ǥ��ä��Ƥ���̱�θ�������褦�ˤʤ�ΤϹ����揢���������κ������Բ�ˤ�����̣���ξ����������Ϥޤ�ޤ�����
���ͻ��塢Ʋ�������糦���ˤϡ�������Ϥ��줿ǯ���Ƥ��ݴɤ���ꤵ�Ф�����ˡ�����̾��뾦������¢���ߤ�135����Ω���¤�Ǥ��ޤ�����
�䲰��2����Ф�áʥ�����ˤ�¢���Ȥ���������ͤ��Ƥ����ƻԤ��ߡ��䲰���ƻԡˡ�1730ǯ�ˤ����������ʪ����Ծ�Ȥ��ơ����Ʋ���ƻԾ�ؤ�ȯŸ�������������꤬�������ޤ�����
���ͻ��塢Ʋ�������糦���ˤϡ�������Ϥ��줿ǯ���Ƥ��ݴɤ���ꤵ�Ф�����ˡ�����̾��뾦������¢���ߤ�135����Ω���¤�Ǥ��ޤ�����
�䲰��2����Ф�áʥ�����ˤ�¢���Ȥ���������ͤ��Ƥ����ƻԤ��ߡ��䲰���ƻԡˡ�1730ǯ�ˤ����������ʪ����Ծ�Ȥ��ơ����Ʋ���ƻԾ�ؤ�ȯŸ�������������꤬�������ޤ�����

���ʳ����ϰ�ǡ�̣������Τ���ȤȤ��ä����ۼ��ؤ˼����ȯŸ���Ƥ��ޤ����������Ǥ���Τ�����٤ä����ͤ���Į��ʸ�����ֳ����Ƥ��ä��ΤǤ������κ������ͤǤϷ����Ф�Ƥ����ˤ⤫����餺��ʸ����ʸ��ǯ�֤ˤ�ϲ��λ���Ȥʤꡢ̣���ˤ����Ƥ��ƹ��äפ�ȻȤä������ʴŸ�����̣�����������ޤ�����
��Ǥ�н��ä����餺�Ȥ���̣�����Ƚн��פ餺����̣���ɤȤ������ǡ��֤���̣���ɤȸƤФ�����ʤ��и����ޤ�����
���줬������̣���ɤǤ���
��Ǥ�н��ä����餺�Ȥ���̣�����Ƚн��פ餺����̣���ɤȤ������ǡ��֤���̣���ɤȸƤФ�����ʤ��и����ޤ�����
���줬������̣���ɤǤ���
��������ˤʤ견���Ȭ��̣������������ϩ��������δ�������̣����Ȭ��̣�����碌����ˤ�ꡢ����Ρ��֤���̣���ɤ�Ʊ�ͤ���̣����̣������������ǯ�Ǥ���̣����Ʀ̣�����碌��̣������֤���̣���ɤȸƤ֤褦�ˤʤ�ޤ�����
�Ƥߤ������ߤ��ȤǤϡ���������ˡ���㴳�㤤�ޤ��������Ƥ���٤Ƶۿ�®�٤�®���Τǡ���˿����Ƥ������֤���1���֤ȡ��Ƥߤ�����û���ʤ�ޤ������θ塢��ʬ���ڤ�Ƥ��顢�����ƹ���Ĥ���ޤ���
�ۿ���֤�Ĺ����������ڤ꤬�Խ�ʬ���ä��ꤹ��ȡ������夬�ä����˿�ʬ��¿���Ĥꡢ������˻��ݤˤ��������ʤึ���Ȥʤ�ޤ������Τ��ᡢ���ι��Ť���Ͽ�ʬ��Ĵ���Ȳ��ٴ������ο��Ȥ�����Ǥ��礦�������ι������Ƥߤ���Ʊ�ͤǤ���
Ʀ�ߤ��ϡ���Ʀ�ΰ������Ƥߤ������ߤ��Ȥ������㤤�ޤ���Ʀ�ߤ��ξ�硢��Ʀ�Τ��٤Ƥ�ȤäƤߤ��̤�Ĥ��ꡢ���������ä�ʴ���ˤ��������˼�������������뤫��Ǥ���
��¤�����Ȥ��Ƥϡ��ޤ���Ʀ���Ҥ��ޤ������θ塢�����ν��̤�1.6���1.7�ܡ����Ѥ�1.5���1.6�ܤˤʤ�ޤǡ��ߵ���3���֡��Ƶ���1.5���֤��餤�����Ƶۿ夵���ޤ������ˡ�0.7�ԡ�cm²�ΰ��Ϥ���1.5���2���־����ޤ��������55���60�����ޤ����ߤ�����¤���ˤ�����ľ��19���30mm��“�ߤ���”��Ĥ���ޤ���
�ߤ��̤�30������顢���餫�������������ä�ʴ���ˤ��������˼��������Τ��ۤ�����48���֤������������ޤ������줬Ʀ���Ǥ��������ϡ���������Ʀ���Ф���0.8���2.0�����ٻ��Ѥ��ޤ���
�Ǥ��夬�ä�Ʀ���ϡ������顼�ǰ��Ϥ��ʤ����٤����������˻Ź����ȯ�ڡ����������ޤ���
�ۿ���֤�Ĺ����������ڤ꤬�Խ�ʬ���ä��ꤹ��ȡ������夬�ä����˿�ʬ��¿���Ĥꡢ������˻��ݤˤ��������ʤึ���Ȥʤ�ޤ������Τ��ᡢ���ι��Ť���Ͽ�ʬ��Ĵ���Ȳ��ٴ������ο��Ȥ�����Ǥ��礦�������ι������Ƥߤ���Ʊ�ͤǤ���
Ʀ�ߤ��ϡ���Ʀ�ΰ������Ƥߤ������ߤ��Ȥ������㤤�ޤ���Ʀ�ߤ��ξ�硢��Ʀ�Τ��٤Ƥ�ȤäƤߤ��̤�Ĥ��ꡢ���������ä�ʴ���ˤ��������˼�������������뤫��Ǥ���
��¤�����Ȥ��Ƥϡ��ޤ���Ʀ���Ҥ��ޤ������θ塢�����ν��̤�1.6���1.7�ܡ����Ѥ�1.5���1.6�ܤˤʤ�ޤǡ��ߵ���3���֡��Ƶ���1.5���֤��餤�����Ƶۿ夵���ޤ������ˡ�0.7�ԡ�cm²�ΰ��Ϥ���1.5���2���־����ޤ��������55���60�����ޤ����ߤ�����¤���ˤ�����ľ��19���30mm��“�ߤ���”��Ĥ���ޤ���
�ߤ��̤�30������顢���餫�������������ä�ʴ���ˤ��������˼��������Τ��ۤ�����48���֤������������ޤ������줬Ʀ���Ǥ��������ϡ���������Ʀ���Ф���0.8���2.0�����ٻ��Ѥ��ޤ���
�Ǥ��夬�ä�Ʀ���ϡ������顼�ǰ��Ϥ��ʤ����٤����������˻Ź����ȯ�ڡ����������ޤ���
�̾ȯ�ڡ������κݤˤϡ�����ʪ��ȯ�ں��Ѥ�¥������˿Ͱ�Ū�˲ò��ʤɤ��ʲ�Ĵ���ޤ���������Ф��ơ��ʲ�Ĵ����������������Ԥ���Ǥ����ȯ�ڡ�������������ˡ���ŷ����¤�פȸƤ�Ǥ��ޤ���
Ʀ�ߤ���Ĺ��ŷ����¤�Τߤ��Ȥ����Τ��Ƥ��ޤ���
Ʀ�ߤ���Ĺ��ŷ����¤�Τߤ��Ȥ����Τ��Ƥ��ޤ���
���Ȥϡ��ơ����ʤɤι�ʪ����Ʀ�ʤɤ˹��ݤ����ܤ����˿���������Τǡ��ߤ�����¤�˷礫���ʤ���ΤǤ��������Ͼ�������ʪ�˼�ݡʹ��ݳ��ˤ��ܼ路��Ŭ����30��ˡ�Ŭ����100��ˤΤ�ȤǶݻ��Ĺ�����ޤ����ܼ��16���֤��餤�в᤹��ȡ��ݻ��ɽ�̤��������ؤ������褯���ӡ��������ߡ��Ϥ����ߡˡ��Ƶ�Ǯ�Τ��Ჹ�٤��徺���ޤ����ƹ��ξ��Ϥ��λ�������γ�β���ۤ�����ú���������ӽФ��ƻ��Ǥ��䤤�ޤ��ʼ�����ˡ������������ܤ�³����ȡ��ܼ����40���֤ǹ����Ǥ��夬��ޤ���
���ˤ�¿���ι��Ǥ�����ޤ��������פʤΤϤ���Ѥ���ʬ����ǡʥץ��ƥ������ˤ䡢�Ǥ�פ��������ǡʥ��ߥ顼���ˤǡ�����餬����¸�߲�����Ʀ���ơ�����ʬ��ȯ�ڡ�������������̣�����ߤ���Ĥ���ޤ���
�ޤ����ߤ��Ť���Ǥϡ����ݤ����Ǥʤ��ֹ���פ�������ݡפ���פ�����̤����ޤ�������ϡ����ι��Ǻ��Ѥˤ�äƤǤ�פ��������ƤǤ������륳�������ݼ褷�������������륳����ȯ�ڤ�¥���ޤ����ޤ��������ݤϡ��ߤ��˻�̣��Ϳ������Ʀ����������������ȯ���¥�ʤ���Ư��������ޤ������Τ褦�ˡ��ߤ��Ť���ˤϹ��ݤȹ��졢�����ݤ��礭�����Ѥ��Ƥ��ꡢͭ�Ѥ�����ʪ�����餵��������ݤʤɤ�ͭ��������ʪ�����뤳�Ȥ����褤�ߤ��Ť���Υݥ���ȤˤʤäƤ��ޤ���
���ˤ�¿���ι��Ǥ�����ޤ��������פʤΤϤ���Ѥ���ʬ����ǡʥץ��ƥ������ˤ䡢�Ǥ�פ��������ǡʥ��ߥ顼���ˤǡ�����餬����¸�߲�����Ʀ���ơ�����ʬ��ȯ�ڡ�������������̣�����ߤ���Ĥ���ޤ���
�ޤ����ߤ��Ť���Ǥϡ����ݤ����Ǥʤ��ֹ���פ�������ݡפ���פ�����̤����ޤ�������ϡ����ι��Ǻ��Ѥˤ�äƤǤ�פ��������ƤǤ������륳�������ݼ褷�������������륳����ȯ�ڤ�¥���ޤ����ޤ��������ݤϡ��ߤ��˻�̣��Ϳ������Ʀ����������������ȯ���¥�ʤ���Ư��������ޤ������Τ褦�ˡ��ߤ��Ť���ˤϹ��ݤȹ��졢�����ݤ��礭�����Ѥ��Ƥ��ꡢͭ�Ѥ�����ʪ�����餵��������ݤʤɤ�ͭ��������ʪ�����뤳�Ȥ����褤�ߤ��Ť���Υݥ���ȤˤʤäƤ��ޤ���

�����Ȥϡ���������Ʀ���Ф�����γ������դǡ�
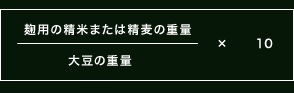
��ɽ���ޤ�������礬�⤯�ʤ�ۤɴŸ��Τߤ��ˤʤꡢ����礬�Ǥ�⤤�Τ���Ťߤ��ʹ����15���30�ˤǡ����������ߤ��δŸ��ߤ���15���25�ˤȤʤ�ޤ����̾�οɸ��Τߤ��ι�����5���10�Ǥ���
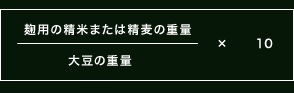
��ɽ���ޤ�������礬�⤯�ʤ�ۤɴŸ��Τߤ��ˤʤꡢ����礬�Ǥ�⤤�Τ���Ťߤ��ʹ����15���30�ˤǡ����������ߤ��δŸ��ߤ���15���25�ˤȤʤ�ޤ����̾�οɸ��Τߤ��ι�����5���10�Ǥ���
�ߤ���ʬ����ȡ��礭��������ˤʤ�ޤ�������ܤ���ߤ��ȸƤФ��ø�������Τߤ�������ܤϡ������ߤ�����ɽ����벫�ߤ��ӤӤ�ø���Τߤ����Ǹ�ϡ��֤ߤ��ȸƤФ���֤ߤ��ӤӤ��ֳ쿧�Τߤ��ǡ�����ߤ��乾�ʹŤߤ���Ʀ�ߤ��ʤɤ������������ޤ���
�����������ΰ㤤��ǻø�κ����Ф�Τϡ�ȯ�ڡ�������˵�����“�ᥤ�顼��ȿ��”�������Ǥ����ᥤ�顼��ȿ���Ȥϡ������Ǥ�����Ʀ�ʤɤΥ��ߥλ�������ȿ�����Ƴ��ѡʳ쿧���Ѳ�����ˤ��뤳�ȤǤ�����������¤��ˡ�ˤ�äƺ������ꡢ�ᥤ�顼��ȿ������ʬ�����ä��ߤ��ۤɳ쿧���ӤӤƤ��ޤ���
��ߤ���Ĥ����硢����Ū����Ʀ�ο�����֤�û�������������˼Ѥޤ����������뤳�Ȥˤ�äƳ��Ѥθ����Ȥʤ����ʤɤο�������ʬ�����������ȤȤ�ˡ������κݤΥᥤ�顼��ȿ�����ޤ���졢����ø���ʤ�ΤǤ���
�դˡ���Ʀ�ο�����֤�Ĺ�������ⲹ��Ĺ���־��Ѥ���ȡ�����Ѥ�����Ǯ�������ƹ��Ǥˤ��ʬ��¥�ʤ���뤿�ᡢǻ���֤ߤ��Ȥʤ�ޤ����ޤ�����¤����ʲ����⤤�ۤɡ��ޤ����δ��֤�Ĺ���ۤɡ�����ǻ���ʤ뷹��������ޤ���
�����������ΰ㤤��ǻø�κ����Ф�Τϡ�ȯ�ڡ�������˵�����“�ᥤ�顼��ȿ��”�������Ǥ����ᥤ�顼��ȿ���Ȥϡ������Ǥ�����Ʀ�ʤɤΥ��ߥλ�������ȿ�����Ƴ��ѡʳ쿧���Ѳ�����ˤ��뤳�ȤǤ�����������¤��ˡ�ˤ�äƺ������ꡢ�ᥤ�顼��ȿ������ʬ�����ä��ߤ��ۤɳ쿧���ӤӤƤ��ޤ���
��ߤ���Ĥ����硢����Ū����Ʀ�ο�����֤�û�������������˼Ѥޤ����������뤳�Ȥˤ�äƳ��Ѥθ����Ȥʤ����ʤɤο�������ʬ�����������ȤȤ�ˡ������κݤΥᥤ�顼��ȿ�����ޤ���졢����ø���ʤ�ΤǤ���
�դˡ���Ʀ�ο�����֤�Ĺ�������ⲹ��Ĺ���־��Ѥ���ȡ�����Ѥ�����Ǯ�������ƹ��Ǥˤ��ʬ��¥�ʤ���뤿�ᡢǻ���֤ߤ��Ȥʤ�ޤ����ޤ�����¤����ʲ����⤤�ۤɡ��ޤ����δ��֤�Ĺ���ۤɡ�����ǻ���ʤ뷹��������ޤ���

�ߤ��ι��ߤϡ����ޤ��ä����ϤǤĤ�����ߤ��ˤ�äƺ��������Ȥ��äƤ�褤�Ǥ��礦������ۤɡ����ܤΤߤ����������Ȥ˰ۤʤäƤ��ޤ�����Ȥ����̴��줫�����̡��̳�ƻ�����Ǥ��ֳ쿧�οɸ��Ƥߤ�����������Ƥ��ޤ����������ɤ��餫�Ȥ�����ø�����ɸ����Ƥߤ���Τ�����������Φ����������Ȥ��ä����ܳ�¦���ϰ�Ǥ����ޤ������Ρ����š�����Ǥ�Ʀ�ߤ��������Ԥ��濴�Ȥ���ᵦ�����ڤ������ⳤ����ϰ�Ǥ���Ťߤ������彣����ǤϴŸ������ߤ����Ƥߤ������ޤ�Ƥ��ޤ���
����Ū�ˡ����μ��बƱ���Ǥ���ФĤ������϶��̤Ǥ�������¤ˡ����֤ˤ�äƤǤ��夬�꤬�Ѥ�뤿�ᡢ�����ˤ�ä���̯����ˡ���ۤʤ�ޤ����ʲ�����ʤߤ����������Ȥΰ㤤�Ǥ���

����ߤ����Ƥߤ�����š�
��¤�̤���ʬ�ह��ȡ���������û����������°���ޤ����������Ȥϡ����ι��Ǻ��Ѥˤ�äƤǤ�פ������������ޤ���ʬ���Ѥ���Τ�ؤ��ޤ����Ƥ������٤�⤯������Ʀ����γ��æ�餷����Τ���ѡ��ƹ���˦�Ҥ��������ʤ�������Ѥ��ޤ�����Ʀ�Ͼ������˼Ѥޤ���������ϼ�Ȥ����忧�����ʤ�����Ǥ����Ѥ���Ʀ�ϼѽ������ä�Ǯ���������ƹ��ȱ��礷�����˵ͤᡢ�ʲ�������Ѳ����ʤ��褦���ݲ�����1���2���ֽ��������ޤ��������β��٤��⤤�Τǡ�����������ݤ�Ư���ޤ���

�����ʹŤߤ����Ƥߤ����ֿ��Ÿ���
�Ƥ����̤Τߤ���Ʊ���褦�˹��ˤ��ޤ�����������Ʀ������ȴ����7���8���ֿ椭���ݲ����������ޤ����֤��ޤ������δ֤˾�����Ʀ�Ͻ�ʬ�ˤ��餫���ʤ�ȤȤ�ˡ�������������ͭ�����쿧���Ѥ�ä���ͭ��˧��������ޤ�������ˤ�ꡢ��¢������夷�ޤ����Ź��ߤ���ߤ��Ȥۤ�Ʊ���Ǥ������������֤ϲƵ���10�����餤���ߵ���1����餤�Ǥ�����ߤ���Ʊ���ǡ�����������ݤ�ȯ�ڤϸ����ޤ���
������ߤ����Ƥߤ����ֿ��ɸ���
��Ʀ�Ͼ�������Ѥ����塢���ȱ�����碌��ŷ����¤�Ǿ��ʤ��Ȥ�10����ʾ���������ޤ�������ˤ�äơ���Ʀ�Τ���Ѥ����Ͻ�ʬ�˲ÿ�ʬ��Ƥ��ޤߤ�Ф�������������ݤ�ȯ�ڤⴰ���Ȥʤꡢ��̣�����ޤ�ޤ����������Ʊ�ʬ�����Ū¿���ˤ⤫����餺����̣�Ȥ��ޤߤΥХ���Ȥ줿����줷���ߤ��Ȥʤ�ޤ���
�������ߤ����Ƥߤ���ø���ɸ���
�̾�ߤ���Ĺ���֤����ƾ�¤����ȡ��ֳ쿧���忧���ޤ������Τ��ᡢø���ߤ��Ǥϡ���¤�����������̤����忧��Ǿ��¤ˤȤɤ��褦�ˤ��ޤ���ø���ο����ߤ��ϸ�������Ʀ��������������٤��⤯�����IJ��������䤫�ʤ�Τ������Ǥ���¤���ǫ���������ޤ�������˿��Ҥ������ˡ�ʤɤ��פ����ꡢ�忧��ʬ���忧¥��ʪ���ʤɤ�������ȡ��ߤ��δ��������ˤ����Ƥ���夫�ʤ��褦��θ���ޤ���
���۸�ߤ����Ƥߤ����ֿ��ɸ���
�۸�ߤ�����ħ�ϡ���γ���⤤��γ�ߤ��ˤ���ޤ����ޤ�����γ��Ĥ�����ˡ��������Ƥ��Ѥ��ޤ����ƹ��ϱ��ڤ���ˤ���������åѡ����̤���������Ʀ�Ⱥ��礷�ޤ���������Ʀ���Ѥ��뤿�ᡢ�ֿ��ߤ��Ȥ��äƤ⡢�忧�����Ūø���˶�ʤ�ΤǤ����츫��γ���ĤäƤ���褦�˸����ޤ������ƤΤǤ�פ�ʤɤμ���ʬ�ϤۤȤ���������Ƥ��ޤ���ʬ�ȤʤäƤ��ޤ���
�����ߤ���ø��������ֿ����Ÿ����ɸ���
�彣�������ܤǤ�������������Ǥ���������Ȥ��ƻ��Ѥ���ޤ�������Ū����Ʀ���Ф�����γ�礬Ʊ���⤷����2�ܤȹ⤯����ˤ���Ʀ�������Ȥ�ʤ���Τ⤢��ۤɤǤ����彣�����Τ�Τ����Ū�������֤�û�����Ÿ���ø���Ǥ����������������ʤ�Ĺ���ֽ�����Ф����ߤ��Ͽɸ����ֿ��Ȥʤꡢ����������¿�������ޤ���
��Ʀ�ߤ����ֳ쿧�ɸ���
����ˡ��Ź��ߡ����������ä���ħ������ޤ������̤�Ʀ�ߤ��ϡ��ߤ��̤�Ĥ���Ȥ���ľ��19mm���٤η꤫�������Ʀ���Ф��ޤ�������ˤϤߤ��̤ꤳ�֤����餤���礭���ˤ��������⤢��ޤ����ߤ��̤��礭���ȹ��Ǥ�Ư���������ʤ�Τǡ�������䤦����˻Ź����Ѥο�ʤ�����42���43�餤�ˡ��Ǥ��Ź��ߤޤ�������˽��Ф�¿�����뤳�ȤǡʻŹ���ʪ�ν��̤�80��ˡ������ο�Ʃ��¥���ȤȤ�ˡ������οʹԤ��ޤ��ޤ������θ塢���ʤ��Ȥ���ưʾ����ŷ�����Ǥ��ä���Ƚ��������ޤ��� Ʀ�ߤ��Ϲ��Ǥˤ��ʬ��ǡ�����������ݤˤ��ȯ���٤����ʤ��Τ���ħ�Ǥ������Τ��ᡢ����Ѥ�����ʬ����ʬ��¿����̣��ǻ�������äιᵤ������ޤ�������ǻ�����鷺���˽�̣�ȶ�̣������ޤ���
����ߤ����Ƥߤ�����š�
��¤�̤���ʬ�ह��ȡ���������û����������°���ޤ����������Ȥϡ����ι��Ǻ��Ѥˤ�äƤǤ�פ������������ޤ���ʬ���Ѥ���Τ�ؤ��ޤ����Ƥ������٤�⤯������Ʀ����γ��æ�餷����Τ���ѡ��ƹ���˦�Ҥ��������ʤ�������Ѥ��ޤ�����Ʀ�Ͼ������˼Ѥޤ���������ϼ�Ȥ����忧�����ʤ�����Ǥ����Ѥ���Ʀ�ϼѽ������ä�Ǯ���������ƹ��ȱ��礷�����˵ͤᡢ�ʲ�������Ѳ����ʤ��褦���ݲ�����1���2���ֽ��������ޤ��������β��٤��⤤�Τǡ�����������ݤ�Ư���ޤ���
�����ʹŤߤ����Ƥߤ����ֿ��Ÿ���
�Ƥ����̤Τߤ���Ʊ���褦�˹��ˤ��ޤ�����������Ʀ������ȴ����7���8���ֿ椭���ݲ����������ޤ����֤��ޤ������δ֤˾�����Ʀ�Ͻ�ʬ�ˤ��餫���ʤ�ȤȤ�ˡ�������������ͭ�����쿧���Ѥ�ä���ͭ��˧��������ޤ�������ˤ�ꡢ��¢������夷�ޤ����Ź��ߤ���ߤ��Ȥۤ�Ʊ���Ǥ������������֤ϲƵ���10�����餤���ߵ���1����餤�Ǥ�����ߤ���Ʊ���ǡ�����������ݤ�ȯ�ڤϸ����ޤ���
������ߤ����Ƥߤ����ֿ��ɸ���
��Ʀ�Ͼ�������Ѥ����塢���ȱ�����碌��ŷ����¤�Ǿ��ʤ��Ȥ�10����ʾ���������ޤ�������ˤ�äơ���Ʀ�Τ���Ѥ����Ͻ�ʬ�˲ÿ�ʬ��Ƥ��ޤߤ�Ф�������������ݤ�ȯ�ڤⴰ���Ȥʤꡢ��̣�����ޤ�ޤ����������Ʊ�ʬ�����Ū¿���ˤ⤫����餺����̣�Ȥ��ޤߤΥХ���Ȥ줿����줷���ߤ��Ȥʤ�ޤ���
�������ߤ����Ƥߤ���ø���ɸ���
�̾�ߤ���Ĺ���֤����ƾ�¤����ȡ��ֳ쿧���忧���ޤ������Τ��ᡢø���ߤ��Ǥϡ���¤�����������̤����忧��Ǿ��¤ˤȤɤ��褦�ˤ��ޤ���ø���ο����ߤ��ϸ�������Ʀ��������������٤��⤯�����IJ��������䤫�ʤ�Τ������Ǥ���¤���ǫ���������ޤ�������˿��Ҥ������ˡ�ʤɤ��פ����ꡢ�忧��ʬ���忧¥��ʪ���ʤɤ�������ȡ��ߤ��δ��������ˤ����Ƥ���夫�ʤ��褦��θ���ޤ���
���۸�ߤ����Ƥߤ����ֿ��ɸ���
�۸�ߤ�����ħ�ϡ���γ���⤤��γ�ߤ��ˤ���ޤ����ޤ�����γ��Ĥ�����ˡ��������Ƥ��Ѥ��ޤ����ƹ��ϱ��ڤ���ˤ���������åѡ����̤���������Ʀ�Ⱥ��礷�ޤ���������Ʀ���Ѥ��뤿�ᡢ�ֿ��ߤ��Ȥ��äƤ⡢�忧�����Ūø���˶�ʤ�ΤǤ����츫��γ���ĤäƤ���褦�˸����ޤ������ƤΤǤ�פ�ʤɤμ���ʬ�ϤۤȤ���������Ƥ��ޤ���ʬ�ȤʤäƤ��ޤ���
�����ߤ���ø��������ֿ����Ÿ����ɸ���
�彣�������ܤǤ�������������Ǥ���������Ȥ��ƻ��Ѥ���ޤ�������Ū����Ʀ���Ф�����γ�礬Ʊ���⤷����2�ܤȹ⤯����ˤ���Ʀ�������Ȥ�ʤ���Τ⤢��ۤɤǤ����彣�����Τ�Τ����Ū�������֤�û�����Ÿ���ø���Ǥ����������������ʤ�Ĺ���ֽ�����Ф����ߤ��Ͽɸ����ֿ��Ȥʤꡢ����������¿�������ޤ���
��Ʀ�ߤ����ֳ쿧�ɸ���
����ˡ��Ź��ߡ����������ä���ħ������ޤ������̤�Ʀ�ߤ��ϡ��ߤ��̤�Ĥ���Ȥ���ľ��19mm���٤η꤫�������Ʀ���Ф��ޤ�������ˤϤߤ��̤ꤳ�֤����餤���礭���ˤ��������⤢��ޤ����ߤ��̤��礭���ȹ��Ǥ�Ư���������ʤ�Τǡ�������䤦����˻Ź����Ѥο�ʤ�����42���43�餤�ˡ��Ǥ��Ź��ߤޤ�������˽��Ф�¿�����뤳�ȤǡʻŹ���ʪ�ν��̤�80��ˡ������ο�Ʃ��¥���ȤȤ�ˡ������οʹԤ��ޤ��ޤ������θ塢���ʤ��Ȥ���ưʾ����ŷ�����Ǥ��ä���Ƚ��������ޤ��� Ʀ�ߤ��Ϲ��Ǥˤ��ʬ��ǡ�����������ݤˤ��ȯ���٤����ʤ��Τ���ħ�Ǥ������Τ��ᡢ����Ѥ�����ʬ����ʬ��¿����̣��ǻ�������äιᵤ������ޤ�������ǻ�����鷺���˽�̣�ȶ�̣������ޤ���
�ߤ���������ȯ�ڿ��ʤǤ�������ˡ����������۹��Ʊ���ˤ��ƻŹ��ߡ�Ʊ���褦�˴������Ƥ⡢�Ǥ��夬��ߤ�����̣������Ʊ���ˤʤ�Ȥ������ȤϤޤ�����ޤ�������ʪ����������ȯ�ڡ������β����Ǥϡ�������郎ʣ�������߹礤������Ū����̣�������Ф���ޤ���
������Τ���Τߤ��Ť���Ǥϡ�¢�����פȸƤӤޤ������ߤ�¢���Ȥˡ��ߤ�����̣������Ф����ǡ������˽��ߤĤ�������ʪ�μ���ʹ��졦�����ݤʤɡˤ䤽��餬Ư���Ķ���郎�ۤʤꡢ��̣�ʤɤˤ���¢��ͭ�θ��������߽Ф���ޤ����������Ϥ����ˤϡ��ʳؤ��Ϥ�ڤФʤ��Ȥ������ȤǤ��礦���������Τߤ����Ĥ����Ƥ����ּ����ߤ��פλ���ˤϡ��Ȥ��Ȥˡ�¢�����פ��ۤʤäƤ������Ȥ����������ޤ���
������Τ���Τߤ��Ť���Ǥϡ�¢�����פȸƤӤޤ������ߤ�¢���Ȥˡ��ߤ�����̣������Ф����ǡ������˽��ߤĤ�������ʪ�μ���ʹ��졦�����ݤʤɡˤ䤽��餬Ư���Ķ���郎�ۤʤꡢ��̣�ʤɤˤ���¢��ͭ�θ��������߽Ф���ޤ����������Ϥ����ˤϡ��ʳؤ��Ϥ�ڤФʤ��Ȥ������ȤǤ��礦���������Τߤ����Ĥ����Ƥ����ּ����ߤ��פλ���ˤϡ��Ȥ��Ȥˡ�¢�����פ��ۤʤäƤ������Ȥ����������ޤ���
��������ߤ��Ȥϡ��ߤ���Ĵ̣����ä�����ΤǤ������Τ��ᡢ�ߤ�����Ĥ�����ʤɡ����Ӥ�����Ȥ��֤�������ޤ��ߤ��˴ޤޤ������ϡ�ŷ��Ĵ̣��������Ĵ̣������Ԥ礷����Τʤɡ����ʤˤ�äƤ��ޤ��ޤǤ���
ŷ��Ĵ̣���Ȥ��Ƥϡ����ۤ享�ۥ�������ʴ���ˤ������ĥ����Ѵ��������ĥ��������ʤޤ��ϥ����ꥨ�����ʤɡˤʤɤ����ꡢ����Ĵ̣���Ǥϡ����륿�ߥ���ʥȥꥦ���˻���Ĵ̣�������ϥ����ʥȥꥦ��ʤɤ�����ޤ���
��������ߤ���ɽ������Ƥ��Ƥ⡢ŷ��Ĵ̣��������ä�����Τ⤢��С�����Ĵ̣��������ä�����Ρ�����˺��ۡ����ĥ��ᡢ������ʴ����ä�����Τʤɡ����������ʼ��ब����ޤ���
ŷ��Ĵ̣���Ȥ��Ƥϡ����ۤ享�ۥ�������ʴ���ˤ������ĥ����Ѵ��������ĥ��������ʤޤ��ϥ����ꥨ�����ʤɡˤʤɤ����ꡢ����Ĵ̣���Ǥϡ����륿�ߥ���ʥȥꥦ���˻���Ĵ̣�������ϥ����ʥȥꥦ��ʤɤ�����ޤ���
��������ߤ���ɽ������Ƥ��Ƥ⡢ŷ��Ĵ̣��������ä�����Τ⤢��С�����Ĵ̣��������ä�����Ρ�����˺��ۡ����ĥ��ᡢ������ʴ����ä�����Τʤɡ����������ʼ��ब����ޤ���
�ߤ��ϼ��ब¿�������줾��������ۤʤ뤿�ᡢ��̣���¤�Ĺû���ޤ��ޤǤ�������Ū�ˤϡ������ʹ��λ����̡ˤ�¿����Τ��ʬ�̤����ʤ���Τۤɾ�̣���¤�û����ȿ�Фˡ���俩���̤�¿�����������֤�Ĺ����Τ�Ʀ�ߤ��ʤɤϾ�̣���¤�Ĺ���ʤ�ޤ���
��̣���¤ϡ����ʤˤĤ�����Ǥ�������¤�Ԥ����뤳�ȤˤʤäƤ��ޤ���������̣�����ȶ�Ʊ�ȹ�Ϣ���Ǥϡ���Ĥδ��Ȥ��Ƽ��Τ褦���ϰϤ�Ŭ���Ǥ����Ƚ�Ǥ��Ƥ��ޤ���
��̣���¤ϡ����ʤˤĤ�����Ǥ�������¤�Ԥ����뤳�ȤˤʤäƤ��ޤ���������̣�����ȶ�Ʊ�ȹ�Ϣ���Ǥϡ���Ĥδ��Ȥ��Ƽ��Τ褦���ϰϤ�Ŭ���Ǥ����Ƚ�Ǥ��Ƥ��ޤ���
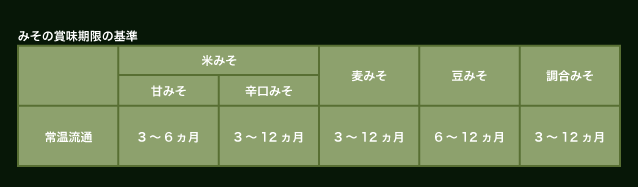
�����ܤ���������������Ƚ�Ǥ���Τ����ΤǤ�������Ȥ��Ƽ��Τ褦������α�դ������֤Ȥ褤�Ǥ��礦��
�ޤ����ߤ��μ���ˤ�äưۤʤ��ΤΡ����ߤ���㤨�����Ƥ��뤳�Ȥ����ޤ������������ä���Τ俧���Τ����ΤϹ��ޤ�������ޤ���
�ޤ������٤��Ȥ��ˡ��ߤ��餷�����ߤ����꤬���뤳�Ȥ�ݥ���ȤǤ�����Ʀ�����������Է齭�����ʽ��ʤɤΤ����Τϡ��褤�ߤ��ȤϤ����ޤ�����˱�̣�����Ƥ��ơ���̣���̣�Τʤ���Ρʤߤ��μ���ˤ�äƤϡ����줬��ħ�ξ��⤢��ޤ��ˡ��������Ѽ��Ǥ��뤳�ȡ�Ǵ�餺�Ϥ��Τ褤���ȡ��ʤ�餫�Ǥ���Ĥ��Τʤ����Ȥ�褤�ߤ��ξ��Ǥ���
�ޤ����ߤ��μ���ˤ�äưۤʤ��ΤΡ����ߤ���㤨�����Ƥ��뤳�Ȥ����ޤ������������ä���Τ俧���Τ����ΤϹ��ޤ�������ޤ���
�ޤ������٤��Ȥ��ˡ��ߤ��餷�����ߤ����꤬���뤳�Ȥ�ݥ���ȤǤ�����Ʀ�����������Է齭�����ʽ��ʤɤΤ����Τϡ��褤�ߤ��ȤϤ����ޤ�����˱�̣�����Ƥ��ơ���̣���̣�Τʤ���Ρʤߤ��μ���ˤ�äƤϡ����줬��ħ�ξ��⤢��ޤ��ˡ��������Ѽ��Ǥ��뤳�ȡ�Ǵ�餺�Ϥ��Τ褤���ȡ��ʤ�餫�Ǥ���Ĥ��Τʤ����Ȥ�褤�ߤ��ξ��Ǥ���
���������ߤ��ϡ��ʤ�٤������˿���ʤ��褦�ˤ���ȤȤ�ˡ�ɬ����¢��¸���ޤ��礦�������˿����ȹ������ݤ��˿����䤹���ʤä��ʼ��������ʤꡢ��̣������ޤ����ͤ�Τߤ��ϡ��Ȥ��Ĥ��ޤ���ζ�����ȴ�����ޤθ��ä���ߤ�ƶ���������ʤ��褦�ˤ��ޤ������뤤�ϡ�̩���ƴ�ʤɤ˰ܤ������ơ�ɽ�̤˥�å��̩�夵���Ƥ��鳸��Τ�褤�Ǥ��礦���ƴ�˰ܤ�������Ȥ��ϡ��ߤ��������˶�ƶ���Ǥ��ʤ��褦��̩�˵ͤ�ޤ����ޤ����ƴ�����Τߤ��ξ��⡢�������ɽ�̤˥�å��̩�夵���Ƥ����ƴ�γ���ȡ���¤�����ʼ����ݤ���ޤ���
��¸����Ȥ�����¢�ˤ������Τϡ���������¸����Ȳ��٤αƶ��dz��ѡʿ����쿧���Ѥ��ȿ���ˤ��䤹��������̣��»�ʤ��뤫��Ǥ���
��¸����Ȥ�����¢�ˤ������Τϡ���������¸����Ȳ��٤αƶ��dz��ѡʿ����쿧���Ѥ��ȿ���ˤ��䤹��������̣��»�ʤ��뤫��Ǥ���
�ߤ���ͥ�줿����Ѥ����Ǥ��뤳�Ȥϡ��縶���Ǥ�����Ʀ�Υ��ߥλ��ΥХ���Ȥ�Ƥ��뤳�Ȥ䡢����Ѥ��������Ǥʤɤ�Ư���Ǿò��ۼ����䤹�����֤�¸�ߤ��뤳�Ȥ����狼��ޤ����ޤ�����Ʀ�λ����¿���ޤޤ���Ρ��������˰�»��û��ˤˤϡ����楳�쥹�ƥ������ͤ���Ư��������Ȥ����Ƥ��ޤ���
���Τ褦�ˡ��ߤ��ˤϤ��ޤ��ޤʷˤ褤��ʬ���ޤޤ�Ƥ���ΤǤ���
���Τ褦�ˡ��ߤ��ˤϤ��ޤ��ޤʷˤ褤��ʬ���ޤޤ�Ƥ���ΤǤ���
�ߤ��˴ޤޤ���ʬ�ϡ����٤ƿ�ʬ���ϲ�����¸�ߤ��ޤ��������ơ��ߤ��μ������μ��ࡦ�̤ˤ�äƤ��ʬ�̤ϰۤʤ�ޤ���
�ߤ���Ź���Ȥ��˻Ȥ���ʬ�ϡ��̾�12������Ǥ���Ʀ�ߤ���Ÿ��ߤ��Ϥ�������侯�ʤ�����ߤ��乾�ʹŤߤ��ˤʤ�Ȥ���˾��ʤ��ʤꡢ5���7��ȤʤäƤ��ޤ���
�ߤ��˴ޤޤ����ϡ����������Ǥ�ȯ������ʪ����������ա����Ǻ��Ѥ�ȥ����뤹�뤦���Ƿ礫���ʤ������ǤϤʤ���ͭ�����ݡʸ���ݤʤɡˤ���������Ư���⤢��ޤ����ޤ�����ʬ��¿���ߤ�������ʪ�γ��Ϥ��ޤ��뤿�ᡢ��ʬ����̣��������ޤǤ˻��֤�������ޤ�����Ʊ���ˤ��δ֤˱����ʱ�̣���ʤ���Ǥޤ��䤫�ˤʤ뤳�ȡˤ��Ƥ���Τǡ���ʬɽ��������Ǥϡ����٤��Ȥ��α�̣��Ƚ�ꤷ��������ΤǤ���
�ߤ��˴ޤޤ����ϡ����������Ǥ�ȯ������ʪ����������ա����Ǻ��Ѥ�ȥ����뤹�뤦���Ƿ礫���ʤ������ǤϤʤ���ͭ�����ݡʸ���ݤʤɡˤ���������Ư���⤢��ޤ����ޤ�����ʬ��¿���ߤ�������ʪ�γ��Ϥ��ޤ��뤿�ᡢ��ʬ����̣��������ޤǤ˻��֤�������ޤ�����Ʊ���ˤ��δ֤˱����ʱ�̣���ʤ���Ǥޤ��䤫�ˤʤ뤳�ȡˤ��Ƥ���Τǡ���ʬɽ��������Ǥϡ����٤��Ȥ��α�̣��Ƚ�ꤷ��������ΤǤ���
��ǯ�����Ƿ��������Ȥ����������顢����������������Ƥ��ޤ������Ȥ˸����ʤΡֿ����ݼ��̤�1��10g���⤬˾�ޤ����פȤ�ȯɽ���衢���ʤα�ʬ��ͭ�̤����ܤ����褦�ˤʤ�ޤ��������η�̡�¿���βù����ʤ���ʬ���뷹���ˤ���ޤ������ߤ��ξ�硢���ˤ�ä�ȯ�ں��Ѥ��礭���Ѥ�äƤ��ޤ������Τ��ᡢ��̣�����ߤ���Ĥ��뤿��ˤϿ��������ڤǡ���ȤΤߤ������뤳�ȤϤ��ޤ��̣������ޤ���
�ߤ���¾�ο��ʤȰ�äơ����Τޤ��٤뤳�ȤϤۤȤ�ɤ���ޤ��顢100g��α�ʬ��ͭ�̤�¿���Ƥ⾯�ʤ��Ƥ⡢�ߤ����Ȥ����ݼ褹��Ȥ��ϡ���ʬǻ�٤�1�餤�Ȥʤ�ޤ���
¾�ο��ʤ���Ӥ��ƤߤƤ⡢�ߤ����ˤ����Ȥ��α�ʬ�ݼ��̤�ɬ������¿���ȤϤ����ޤ��ޤ����ߤ�����Ĥ���Ȥ��⡢��äפ������ʤɤι��פ�С�1��ʬ�Τߤ����̤餹���Ȥ��Ǥ��ޤ���
����ȤʤäƤ���Τϡ��ʥȥꥦ��β���ݼ褬��찵�ʤɤθ����ˤʤ�ȹͤ����Ƥ������Ǥ������ʥȥꥦ��ϥ��ꥦ���Ʊ�����ݼ褹��ȡ��γ�����������䤹���ʤ�ޤ����Ǥ����顢���ꥦ���¿���ޤ��в�����ڤ���ࡢ������Υ參��ʤɤ��Ȥ߹�碌�뤳�Ȥǡ��ʥȥꥦ��β���ݼ���ɤ����Ȥ��Ǥ���ΤǤ���
�ߤ���¾�ο��ʤȰ�äơ����Τޤ��٤뤳�ȤϤۤȤ�ɤ���ޤ��顢100g��α�ʬ��ͭ�̤�¿���Ƥ⾯�ʤ��Ƥ⡢�ߤ����Ȥ����ݼ褹��Ȥ��ϡ���ʬǻ�٤�1�餤�Ȥʤ�ޤ���
¾�ο��ʤ���Ӥ��ƤߤƤ⡢�ߤ����ˤ����Ȥ��α�ʬ�ݼ��̤�ɬ������¿���ȤϤ����ޤ��ޤ����ߤ�����Ĥ���Ȥ��⡢��äפ������ʤɤι��פ�С�1��ʬ�Τߤ����̤餹���Ȥ��Ǥ��ޤ���
����ȤʤäƤ���Τϡ��ʥȥꥦ��β���ݼ褬��찵�ʤɤθ����ˤʤ�ȹͤ����Ƥ������Ǥ������ʥȥꥦ��ϥ��ꥦ���Ʊ�����ݼ褹��ȡ��γ�����������䤹���ʤ�ޤ����Ǥ����顢���ꥦ���¿���ޤ��в�����ڤ���ࡢ������Υ參��ʤɤ��Ȥ߹�碌�뤳�Ȥǡ��ʥȥꥦ��β���ݼ���ɤ����Ȥ��Ǥ���ΤǤ���